重点政策を動画で簡単にわかりやすく説明します。
ヘリコプターのパイロットだったころ、私は教官から「遠方目標を定めること」の重要性を教わりました。航空機を操縦する際には、できるだけ遠くの分かりやすい目標(遠方目標)を定め、その上で現在地との間に中間目標を置くことにより、気象の変化などで機体の位置に影響があっても、迷うことなく目的地を目指すことができます。
私は、「同じような考え方は、政治の世界においてもあてはまる」と考えています。県が提供する多くの行政サービスは、一人ひとりの県民生活に密接に関わり、その暮らしぶりに大きな影響を与えるものです。だからこそ、将来を見通し、「県のあるべき姿」へのしっかりとしたビジョン(遠方目標)を持ちながら県政の推進にあたることが重要だと考えています。
県として取り組むべき課題は非常に幅広く、また、県民生活に関わる社会問題が多様化・複雑化する中にあって、私は、民間の力を可能な限り活用することを常に意識してきました。そして、今後さらに加速する人口減少社会に向けては、宮城県という行政組織も不断の改革を続けていくことに加え、これまで以上に県民や民間企業、NPO団体など多様な方々とともに、それぞれが持つ力を結集していく必要があります。
私たちには、震災からの復旧・復興に関係者が手を携えて取り組んできた実績があります。その経験も踏まえながら、今後とも「民の力」を最大限に活かした県政運営に努めてまいります。
私の人生に大きな影響を与えた松下政経塾の塾訓に「素直な心で衆知を集め」という一節があります。私はそれを、「素直な心とは、全てのものをいったん自分の中に受け入れること」と理解しています。
私はこれまでも、県政課題の解決に向け現場に何度も足を運び、多くの当事者の声に真摯に耳を傾けてまいりました。今後とも虚心坦懐に、素直な心で衆知を集めることを心掛けてまいります。
また、様々な課題の解決に向けては、基礎自治体として県民の皆様に接する機会の多い市町村と共通理解を持ち、連携しながら対応していくことが不可欠です。良好なパートナーシップのもと、圏域ごとの課題に応じた支援や広域的な視点に基づく調整など、県に求められる役割をしっかりと果たしてまいります。
就任1期目に打ち出した「みやぎ発展税」には、その当時、多くの厳しい声をいただきました。一方で、私には「これからの県土の発展には、支店経済を背景としてサービス産業に大きく依存した宮城県経済の構造をバランスの取れたものにしていかなければならない」との強い思いがありました。関係者からのご理解を得られるよう、誠心誠意の説明を尽くしながら企業誘致をはじめとする施策の充実を図った結果、現在の宮城県は自動車産業や半導体産業の拠点となり、多くの雇用が生まれたことにより、「県内総生産10兆円」を達成するに至りました。
社会が発展する過程においては対立と調和が伴いますが、その調整や判断は政治の役割です。今後とも、私は何が全体の利益となるのか、熟慮を重ねながら県政を推進してまいります。
人口減少に立ち向かう!
宮城・東北の発展に向けた
新たな地方創生への挑戦
県民の皆様からの負託を受け、私が県政の舵取り役を務めることとなってから、間もなく20年となります。陸上自衛隊東北方面航空隊に配属されていた時、ヘリコプターのパイロットとして大空から眺めた宮城県の姿に大きな将来性を感じたことが、その後、私が政治の世界に身を置くこととなった原点です。
改めてこれまでの約20年間を振り返ると、宮城県は岩手・宮城内陸地震やリーマンショック、東日本大震災、新型コロナウイルス感染症など、度重なる災害や逆境に直面しながらも、県民の皆様や多くの関係者と一丸となってそれを乗り越え、次なる飛躍へのステップにしてまいりました。
とりわけ、2011年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの県民のかけがえのない生命や財産を奪い、県内企業の経済活動にも計り知れない大きなダメージを与えました。一方で、私はこれからの県民生活のあり方や人口減少等の社会構造の変化を考えた時、「『復旧』にとどまらない抜本的な『再構築』」や「現代社会の課題を解決する先進的な地域づくり」を形にしていくことが、自らに課せられた大きな役割であると覚悟を決め、被災地の復興に邁進してまいりました。発生から14年あまりを経て、ハード面の復旧はほぼ完了しましたが、被災された方々の心のケアや福島第一原子力発電所事故への対応など、長期的な取組が求められる課題が残っており、引き続き被災地に寄り添った対応が求められております。
また、2020年2月に県内で初めての感染が確認された新型コロナウイルス感染症に関しては、感染拡大の波が繰り返される中で、日常生活における感染防止対策へのご協力や活動の自粛のお願い、事業者の皆様への営業時間の短縮要請など、極めて制約の多い対応をお願いすることになりました。5類感染症への位置づけ変更を経て、昨年4月に通常の医療提供体制に移行するまでには、結果として約4年間を要したところです。改めて、県民・事業者の皆様のご協力に対し心から感謝を申し上げるとともに、今後仮に同様の事態が起きた場合でもしっかりと対応できるよう、事前の備えを万全に講じておくことの重要性について、思いを強くしたところです。
そして今、宮城県には、人口減少という静かな、しかし大きなうねりが押し寄せています。この20年間、私は人口減少を見据え企業誘致に全力で取り組み、これまでに2万7千人を超える雇用創出を実現いたしました。しかし、少子化等の影響による人口減少のスピードはさらに加速しており、企業誘致といった施策だけでは対応が難しい状況に至っております。国の研究機関の推計では、2020年から2045年までの25年間で、宮城県の人口は40万人近く減少することが見込まれています。私たちがこれまで経験したことのない急激な人口減少は、働き手の確保や地域コミュニティの維持、公共インフラの管理など、様々な分野での深刻な影響が懸念されます。
しかし、きたるべき人口減少社会という現実から目をそらすことなく、将来を見据えた布石を打つことで、新型コロナウイルス感染症をきっかけとしてリモートワーク等の新しい働き方が広まったように、その影響を緩和し、新たな発展の足がかりとすることは不可能ではありません。この6月に、国は「地方創生2.0基本構想」を公表しましたが、その目指す姿は、私が知事就任以来思い描いてきた「生まれてよかった、育ってよかった、住んでよかった」と思える宮城県の姿とも重なり合うものです。幾多の困難から立ち上がってきたこれまでの経験を活かし、人口減少という難局にも県民の皆様と一丸となって立ち向かい、将来に向かって持続可能な宮城県を実現するために、私は、今後4年間への新たなチャレンジを決意いたしました。
私は、2023年9月から2年間、全国知事会会長を務めました。この間、私は「結果を残す知事会」をスローガンに、都道府県単独では実施が難しい海外へのプロモーション活動に、全国知事会として派遣団を組織して取り組んだほか、各都道府県が順番に開催することが慣例となっていた様々な取組の見直しを訴えるなど、人口減少を前提とした行政のスリム化も念頭に置きながら、全国的な課題の解決に向け具体的な道筋を示してまいりました。
東日本大震災に際し全国からいただいた多大なるご支援への感謝と恩返しの気持ちからお引き受けしたこの2年間の経験と、各都道府県との間に築き上げた強固なネットワークをもとに、宮城県がこれまで以上に豊かさや活力にあふれ、東北地方をリードする存在となるべく、全力を注ぎたいと考えております。
この政策集は、これからの4年間に私が取り組もうと考えている政策の一端をお示しするものです。
県民の皆様におかれましては、引き続き、格別のご理解とご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
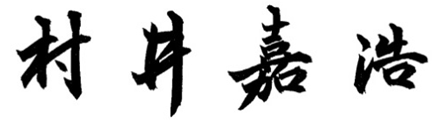
政治家としての私を支えるものの多くは、自衛隊と松下政経塾で教わったことです。「松下政経塾」は、パナソニックの創業者である松下幸之助さんが、未来のリーダーを育成するとの強い思いのもと設立したものです。
松下幸之助さんは、長年にわたり「PHP運動」を提唱しました。「PHP」とは「Peace and Happiness through Prosperity(繁栄によって平和と幸福を)」の頭文字を取ったもので、物と心の両面での繫栄を実現していくことを通じ、真に平和で幸福な社会を実現するという考え方です。
東日本大震災の発生から約10年となる2020年12月に公表した宮城県の長期総合計画「新・宮城の将来ビジョン」には、宮城県が目指す姿として次のような記述があります。
「私たちが目指す10年後の姿は、震災からの復興を成し遂げ、民の力を最大限に生かした多様な主体の連携により、これまで積み重ねてきた富県宮城の力が更に成長し、県民の活躍できる機会と地域の魅力にあふれ、東北全体の発展にも貢献する、元気で躍動する宮城です。
そして、県民一人ひとりが、安全で恵み豊かな県土の中で、幸福を実感し、いつまでも安心して暮らせる宮城です。」
私は、宮城県知事をお引き受けして以来、県民の皆様の幸福を実現するためには、まずはしっかりとした経済基盤を築き、そこから創出された富を循環させることを通じて、活力や安らぎに満ちた県土を築くことが不可欠と考え、様々な取組を進めてまいりました。
これからも、「松下政経塾」の門を叩いた時の思いを忘れることなく、「富県宮城」の実現に向け、全力を尽くしてまいります。
ヘリコプターのパイロットだったころ、私は教官から「遠方目標を定めること」の重要性を教わりました。航空機を操縦する際には、できるだけ遠くの分かりやすい目標(遠方目標)を定め、その上で現在地との間に中間目標を置くことにより、気象の変化などで機体の位置に影響があっても、迷うことなく目的地を目指すことができます。
私は、「同じような考え方は、政治の世界においてもあてはまる」と考えています。県が提供する多くの行政サービスは、一人ひとりの県民生活に密接に関わり、その暮らしぶりに大きな影響を与えるものです。だからこそ、将来を見通し、「県のあるべき姿」へのしっかりとしたビジョン(遠方目標)を持ちながら県政の推進にあたることが重要だと考えています。
県として取り組むべき課題は非常に幅広く、また、県民生活に関わる社会問題が多様化・複雑化する中にあって、私は、民間の力を可能な限り活用することを常に意識してきました。そして、今後さらに加速する人口減少社会に向けては、宮城県という行政組織も不断の改革を続けていくことに加え、これまで以上に県民や民間企業、NPO団体など多様な方々とともに、それぞれが持つ力を結集していく必要があります。
私たちには、震災からの復旧・復興に関係者が手を携えて取り組んできた実績があります。その経験も踏まえながら、今後とも「民の力」を最大限に活かした県政運営に努めてまいります。
私の人生に大きな影響を与えた松下政経塾の塾訓に「素直な心で衆知を集め」という一節があります。私はそれを、「素直な心とは、全てのものをいったん自分の中に受け入れること」と理解しています。
私はこれまでも、県政課題の解決に向け現場に何度も足を運び、多くの当事者の声に真摯に耳を傾けてまいりました。今後とも虚心坦懐に、素直な心で衆知を集めることを心掛けてまいります。
また、様々な課題の解決に向けては、基礎自治体として県民の皆様に接する機会の多い市町村と共通理解を持ち、連携しながら対応していくことが不可欠です。良好なパートナーシップのもと、圏域ごとの課題に応じた支援や広域的な視点に基づく調整など、県に求められる役割をしっかりと果たしてまいります。
就任1期目に打ち出した「みやぎ発展税」には、その当時、多くの厳しい声をいただきました。一方で、私には「これからの県土の発展には、支店経済を背景としてサービス産業に大きく依存した宮城県経済の構造をバランスの取れたものにしていかなければならない」との強い思いがありました。関係者からのご理解を得られるよう、誠心誠意の説明を尽くしながら企業誘致をはじめとする施策の充実を図った結果、現在の宮城県は自動車産業や半導体産業の拠点となり、多くの雇用が生まれたことにより、「県内総生産10兆円」を達成するに至りました。
社会が発展する過程においては対立と調和が伴いますが、その調整や判断は政治の役割です。今後とも、私は何が全体の利益となるのか、熟慮を重ねながら県政を推進してまいります。
私は、これまで築き上げてきた宮城県の姿を、さらに活力に満ちたものとするため、今後4年間に向けてのスローガンを以下のとおり掲げます。
また、特に力を入れて取り組むものとして、「人口減少に負けない、豊かさあふれるみやぎの実現」と「東北をリードし、けん引するみやぎの実現」の2点を重点項目とするほか、「新・宮城の将来ビジョン」に基づく取組を推進してまいります。
人口減少に立ち向かう!
宮城・東北の発展に向けた
新たな地方創生への挑戦
日本国内の人口動態を見ると、総人口の減少、とりわけ15歳から64歳までの生産年齢人口の減少が続いており、コロナ禍でやや落ち着きを見せた東京圏への人口流出も、現在は拡大傾向にあります。
それは宮城県においても同様であり、県の総人口は2003年の約237万人をピークに減少傾向が続いています。国の将来推計では2045年の人口は約192万人まで落ち込み、これまで増加傾向にあった仙台都市圏の人口も減少に転ずることが見込まれています。
その背景としては、婚姻数や出生数がここ10年間で3割を超える大幅な減少となっているほか、10代後半において進学による他県からの転入が多い反面、就職等のタイミングである20代にはそれを上回る転出超過となっていることが挙げられます。
人口減少の影響は、様々な方面に及ぶことが懸念されます。生産年齢人口の減少は県内産業の労働力不足や競争力低下の要因となり、農山漁村地域の過疎化が進行することによる地域活力の低下や、日々の生活に不可欠なサービスが提供困難となることも想定されます。公共インフラや様々な施設・設備の維持管理や災害発生時の復旧対応が困難となることも考えられます。
人口推計が示す将来は、確実にやってきます。しかし、私は手をこまねいてその時を待つのではなく、DXの推進による県内産業の生産性向上や「民の力」の更なる活用により、その影響を最小限に食い止めながら、持続可能な地域づくりを実現してまいります。
私はこれまで、県民の皆様に「生まれてよかった、育ってよかった、住んでよかった」と思っていただける県土の実現を目指し、県政を推進してまいりました。それは、国が「地方創生2.0基本構想」で示した「『強い』経済」「『豊かな』生活環境」「新しい日本・楽しい日本」とも方向性を同じくするものです。
一方で、県内の現状は、仙台周辺地域を除く多くの市町村が人口減少下にあり、将来にわたり安心して暮らすことのできる地域づくりは、以前にもまして喫緊の課題となっています。
そのため、現場の声に丁寧に寄り添いながら、各地域の状況に応じた活性化や魅力の向上を図り、希望に満ちた未来を創造する「みやぎ版地方創生」の取組を強化してまいります。
農林水産業は、県の基幹産業として大きな役割を果たしています。また、食料生産や資源の供給にとどまらず、環境保全や災害の防止、地域文化の継承など、農林水産業には多くの機能があり、その重要性に対する評価も高まっています。
一方で、近年は温暖化や海水温上昇などの気候変動が、農林水産物の収穫量や漁獲量に大きな影響をもたらしており、先進的な技術を積極的に導入し競争力を強化することや、環境変化を踏まえた新たな取組への対応も求められるところです。
私は、宮城の農林水産業がこれからも持続可能で地域を支え続ける存在となるよう取組を強化し、高い収益構造の実現を目指します。
宮城県は、2020年9月に都道府県では全国初となる「デジタルファースト宣言」を行い、その後もデジタル分野に関する専門組織を設けるなど、DX先進県を目指して取組を強化してきました。東日本大震災の経験を踏まえた災害時の避難を支援するアプリは着実に普及が進んでおり、昨年9月の運転免許センターや県税事務所を筆頭に、県の窓口におけるキャッシュレス決済も拡大を図っているところです。
しかし、デジタル化の取組に関するアンケート調査では、約半数の県内企業から「あまり進んでいない」「進んでいない」と回答があり、中小企業等を中心とした支援を強化する必要があります。また、日進月歩で進化を続けるDXの推進には、それを担う人材の育成が不可欠です。
私は、DXの推進により日々の県民生活をより便利で暮らしやすいものとするよう取り組んでまいります。
半導体は身の回りの様々な製品に使われており、日々の生活に必要不可欠な存在です。また、その市場規模が拡大を続ける中、世界各国で誘致競争が盛んに行われており、日本政府による支援も行われているところです。
宮城県には、世界有数の半導体製造装置メーカーである東京エレクトロンのグループ企業が立地し、開発・製造に関する一大拠点として大きな経済効果をもたらしています。また、宮城県は、公共インフラの環境が整っていることや良好な交通アクセスのほか、東北大学をはじめ多くの研究施設や関連企業が集積するなど多くの利点を有しており、これまでの誘致活動で得られた知見も活かした企業誘致を進め、日本における半導体生産の重要拠点となる「みやぎシリコンバレー」の実現を目指します。
宮城県は豊かな海の幸・山の幸があり、松島をはじめとする観光資源も多く、首都圏との交通アクセスも良好であるなど、生活に適した環境が整っています。
一方、首都圏等と比較すると就職先が限られ、希望する業種が選びにくいといった背景から、県内の大学生の多くは就職のタイミングで宮城県を離れる傾向があります。
そのため、若者に魅力ある職場づくり・地域づくりを推し進め県内定着を促進するとともに、若い世代の可能性を最大限に伸ばす教育環境の整備を進めます。
また、多くの業界において人材不足が深刻化する中で、外国人材の活躍は不可欠であり、その受入れや共生に向けた体制づくりを図ります。
全国と比較しても東北地方の人口は急速に減少しており、人口減少は宮城県の課題であると同時に、東北地方全体に向けられた厳しい現実でもあります。
一方で、東北地方は日本における食料供給基地として大きな役割を果たしてきたほか、近年は自動車産業や半導体産業の一大拠点として、県境をまたいだ連携を深めながらその存在感を高めています。人口減少問題についても、各県が思いを1つに連携し、強い覚悟を持って立ち向かうことにより、持続可能な未来を切り開いていく必要があります。
私は、東北各県に培われてきた絆を大事にしながら、全国知事会会長としての経験も踏まえ、東北をリードし、けん引する気概を持って、この難局に対応してまいります。
高い食料自給率や自動車産業等の集積など、東北各県には共通の強みがあります。また、各県それぞれの取組だけでなく、例えば地域ごとの魅力ある産品を東北一体となって連携してPRすることにより、更なる市場規模の拡大が図られると考えます。さらに、東北大学をはじめ東北各地には世界有数の教育・研究機関も存在しており、県境をまたいだ相互利用を促進することで、各県の産業基盤の底上げも期待されます。
私は、幅広い関係者が連携し、東北が一丸となった産業振興を推し進めることにより、東北が地方創生のモデルとなり、若い世代にも選ばれる地域となることを目指します。
東北地方は、四季折々の美しい自然や各地に伝わる伝統的なお祭り、多彩な食文化など、多くの魅力にあふれた地域です。東日本大震災の発生後は、「三陸復興国立公園」や「みちのく潮風トレイル」の指定が進んだほか、この6月には「東北絆まつり」が大阪・関西万博の会場を盛り上げました。
しかし、特に海外から日本を訪れるインバウンド層には、東北の魅力が十分に伝わっているとは言い切れません。また、受入体制も脆弱であり、各観光地が連携して新たなプランを提案するなど、一体となった取組を強化することで、より大きな相乗効果が生み出されます。
私は、宮城県の持つ海外に開かれた空港、港湾の有する機能を最大限に活かすことや、来年1月からご協力をいただく「宿泊税」を活用した観光資源の更なる魅力向上とあわせ、東北全体の持つ可能性を国内外に発信することにより、多くの人々が行き交い活気に満ちた東北を実現します。
現在、宮城県では2021年度から10年間を計画期間とする総合計画「新・宮城の将来ビジョン」に基づく様々な取組を進めています。この計画は、東日本大震災から10年という節目に、本格的な人口減少社会の到来や新型コロナウイルス感染症の感染拡大といった時代の大きな転換点を迎える中で、宮城の持続可能な未来を実現すべく策定したものです。それまでの「宮城の将来ビジョン」の理念を引き継ぎつつ、子育て支援や教育分野に特化した新たな柱を打ち出すとともに、震災からの復興の完遂に向けた内容を盛り込んでいます。
引き続き、県民の皆様が幸福を実感し、いつまでも安心して暮らせる宮城県を実現するため、「新・宮城の将来ビジョン」に基づく取組を推進してまいります。
2024年における宮城県の出生数は11,242人と、10年前と比較して3割以上減少しています。少子化の背景には、経済的な不安定さや出会いの機会の減少、仕事と子育ての両立の難しさなど、様々な要因が指摘されております。多様な価値観や考え方を尊重するとともに、結婚し、子どもを産み育てたいという方の希望を叶えるためにも、切れ目のない支援が不可欠です。
また、増加を続ける児童虐待への対応のほか、子どもの貧困やヤングケアラーなど、様々な困難を抱える子どもたちへの支援も大きな課題であり、児童相談所の体制強化や子ども食堂をはじめとする民間の取組へのサポートを推進する必要があります。
あわせて、子どもたちが成長する過程で大きな役割を担う学校生活に関しては、豊かな人間性や社会性、健やかな心身を育むとともに、グローバル化をはじめ社会の変化が加速する中において、一人ひとりの子どもたちが自らの将来をしっかりと考え、それを実現するための幅広い資質・能力を身に付けられるよう、子どもたちの豊かな学びを支えていくことが重要です。
私は、少子化対策には腰を据えた長期的な対応が不可欠と考え、県独自の取組を更に充実させるため、2021年度に「次世代育成・応援基金」を創設し、結婚応援パスポートの導入や不妊検査・不妊治療への支援制度の創設、県立都市公園へのプレイパークの整備などを進めてまいりました。加えて、今年度からは、子どもが生まれた世帯の経済的負担の軽減を図るため、子育て支援パスポートを通じて地域ポイントを付与する取組をスタートしております。
これからも、若い方々や次の時代を担う子どもたちが身体的・精神的・社会的に幸せな状態(ウェルビーイング)で日々の生活を送ることができるよう、「社会全体で支える宮城の子ども・子育て」として、以下の4つの方向性に沿った取組を進めてまいります。
少子高齢化や人口減少が進む中においても、誰もが社会の一員としてその個性や能力を発揮できる環境を整えていくことは、日々の生活を豊かにするだけでなく、地域の活力を維持していくためにも非常に重要です。
一方で、特に女性の活躍や障害者雇用の促進に向けては更なる取組が求められているほか、留学や技能実習などを背景に県内の在留外国人は増加傾向にあり、国籍や民族等の違いに関わらず活躍に向けた機会が等しく提供され、地域で安心して生活できる多文化共生社会の実現も大きな課題となっています。
また、文化芸術に親しむ機会やスポーツ活動への参加などを通じて、県民一人ひとりが生活の豊かさや安らぎを実感できる環境づくりを進めることや、あらゆる世代を対象として、県民それぞれのライフステージに応じた学びの機会が適切に提供される必要があります。
さらに、県民の皆様が安全・安心な日々の生活を営む上で欠かせない医療・保健・福祉に関する各種サービスは、現場を支える人材の不足が顕著となっており、その確保は喫緊の課題であるほか、施設の偏在等の課題にも適切に対応していく必要があります。また、障害のある人もない人も、お互いを尊重し支え合いながら生活できる環境の実現も急務です。
このほか、地域コミュニティの維持に極めて大きな役割を果たしている公共交通の確保や、安全・安心な地域社会づくりに向けた備えも、県民生活の安定には必要不可欠なものです。
上記の課題を踏まえ、「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」として、以下の5つの方向性に沿った取組を進めてまいります。
私は、就任1期目の2008年に導入した「みやぎ発展税」を活用し、橋梁の耐震化などのインフラ強化や防災体制の整備などを推進してきたほか、東日本大震災の教訓を踏まえ、「災害に強いまちづくり宮城モデル」を提唱するなど、多くの取組を進めてまいりました。
しかし、全国ではその後も大規模な自然災害が相次いでおり、宮城県においても平成27年9月関東・東北豪雨や令和元年東日本台風のほか、2021年・2022年には福島県沖を震源とする地震により大きな被害が発生しました。
東日本大震災を経験した身として、災害から県民の生命・財産を守ることは何よりも優先すべき課題です。そのため、私は、原子力災害や自然災害が発生した際にも迅速な情報提供や円滑な避難をサポートするアプリの運用をスタートするなど、実効性ある防災・減災の実現に向け不断の取組を進めているところです。一方で、災害への備えは行政のみが取り組むものではなく、自助・共助・公助それぞれの観点から、関係者がその役割に応じて日ごろから備えを講じていくことが肝要です。
また、老朽化が進む各種の公共インフラについては、災害への備えだけでなく、維持管理や長寿命化対策を長期的な観点に基づいて進めることにより、安全性や信頼性を持続していく必要があります。
さらに、2050年における温室効果ガス排出実質ゼロの実現に向けた取組をオールみやぎで推進するほか、ラムサール条約湿地に登録され今年で30年となる伊豆沼・内沼をはじめとする豊かな自然環境を後世に引き継ぐことなど、自然と人間の共生に向けた取組も非常に重要です。
このような現状認識のもと、「強靱で自然と調和した県土づくり」として、以下の4つの方向性に沿った取組を進めてまいります。
私は、知事就任以来、自動車関連産業や高度電子機械産業、食料品製造業などの誘致・集積に一貫して力を入れてまいりました。その背景には、長期的な人口減少、とりわけ労働力人口の減少が見込まれる中で、県内経済の冷え込みを回避するためには、交通環境の良さや充実した公共インフラ、東北大学をはじめとする教育・研究機関の立地といった多くのポテンシャルを活かし、産業構造の転換を図らなければならない、具体的には、それまで手薄となっていたものづくり産業を根付かせることが何よりも必要と考えたからです。その後、東日本大震災等の影響はありましたが、製造業出荷額は着実に増加を続け、2018年度には県内総生産10兆円を達成することができました。人口の急速な減少など厳しい状況は続きますが、さらなる高みを目指していかなくてはなりません。
一方、地域経済の活性化などに大きく寄与している観光産業は、新型コロナウイルス感染症からの影響は脱しつつあるものの、まだまだ脆弱な状況です。インバウンドの誘致に関しては国内各地と比較して大きく水を空けられていることから、受入環境の整備や観光資源の磨き上げなどに力を入れる必要があります。
また、農林水産業は、地域の基幹産業としての役割だけでなく、昨今のコメの価格高騰や不透明な世界経済情勢などを踏まえると、食料安全保障の観点からもその重要性が再認識されています。
農業については、農地の大区画化や収益性の高い作物の導入などを推進するほか、食品産業との連携を図りながら園芸生産の拡大を図ります。水産業については、産業規模は震災前の水準まで回復したものの、海洋環境の変化による水揚げへの影響などもあり、新しい技術の導入などを進めながら、環境と調和した活力ある産業へと転換を図ります。林業については、2022年度に開校した「みやぎ森林・林業未来創造カレッジ」を通じて林業従事者等の育成を図りながら、県産木材の新たな需要創出等を進めていきます。
一方、20代の県外流出が続いており、多くの業界において人手不足が経営上の大きな課題となっていることから、UIJターンの推進や女性・高齢者等も柔軟に働くことのできる環境整備、外国人材の活用など、様々な手法を組み合わせた人材の育成・確保が求められています。
また、産業基盤の整備については、物流の効率化等に向けた公共インフラの整備に加え、仙台空港や仙台塩釜港の更なる利用拡大に向けたプロモーション等の取組を進める必要があります。
上記課題の解決に向け、「富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進」として、以下の5つの方向性に沿った取組を進めてまいります。
東日本大震災の発生から、来年3月で15年となります。「創造的な復興」の実現を目指した「宮城県震災復興計画」に基づく10年間の取組を経て、現在は「新・みやぎの将来ビジョン」において「被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポート」を基本方向の柱の一つに掲げ、個々の課題に応じた丁寧な対応に努めているところです。
関係者のご尽力や全国からの多大なご支援もあり、住まいの確保や市街地の再生などのハード事業は、現在までにほぼ完了しています。一方で、心のケアや子どもたちに対する支援などは、中長期的な課題としてこれからも当事者に寄り添ったフォローが必要であるほか、被災された方々の生活やなりわいの再建状況も決して一様ではないことから、継続的な支援を行ってまいります。
また、安全・安心な県産農林水産物を海外も含めた各地に提供できるよう、現在も放射性物質検査による安全性の確認を行っていますが、海外との取引には現在もなお一部に制限があることから、粘り強い情報発信や販路の開拓が必要です。
さらに、震災の教訓や記憶の伝承に向けては、2022年に「震災伝承みやぎコンソーシアム」を設立し、多様な主体が連携した取組が芽生えていますが、持続的な活動を支え、継続した情報発信を行うためには、人材育成などの取組が重要となります。
今後とも、全ての県民の皆様に復興を実感いただけるよう、息の長い支援に取り組んでまいります。
© YOSHIHIRO MURAI, All Rights Reserved.